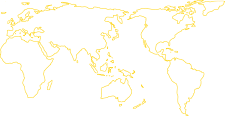2025年5月10日
はじめに
4月14~15日にシンガポールで開催された会議(AVP前号参照[1] )に出席した際、同地の研究者たちと意見交換してきた。米国とも中国とも異なる視点を持つ人たちとやり取りできたことはとても良い刺激になった。本号では、そんなやり取りの中で1人のシンガポール人研究者が投げかけた、「日米同盟の解消」に関する質問を2つ紹介する。私がどう答え、その質問をきっかけに何を考えたかについても当然述べる。読者にも「自分ならどう答えるか?」と考えながら読んで頂ければ、嬉しい。
「防衛費をGDP比3%にしなければ、同盟を解消する」と米国に言われたら?
最初の質問は、「トランプが『日本が防衛費をGDP比3%にしなければ、日米同盟を解消する』と言ってきたら、日本はどうするか?」というものだった。
この問いを受けた時、私は「なるほど」と思った。トランプは大統領1期目の在任中、非公式の場で〈NATOからの完全脱退〉を口にしていたと言われる。その後もトランプがNATO加盟国の国防費負担が少ないことに不満を示し続けていることは周知の事実。「(欧州諸国が国防費を増やさなければ)ロシアが攻撃してきても助けるつもりはない」と言ったかと思えば、NATO加盟国に国防費のGDP比を5%に引き上げるよう求めたりもしている。[2]
トランプにとっては日米同盟も〈聖域〉ではない。2019年7月には、米軍駐留費負担を4倍(年80億ドル=実際にかかる直接経費の3倍!)にするよう、日本政府に求めたと言われている。[3] 最近も、「米国は日本を守るために何千億ドルも払う。全額を米国が負担する。日本は何も支払わない」「(日米安保条約で)我々は日本を守らなければならないが、日本は我々を守る必要がない」等々、〈フェイク〉や〈言い掛かり〉も交えて言いたい放題。[4] その人事が4月8日に議会承認されたエルブリッジ・コルビ―国防次官は、3月に開催された上院の公聴会で「日本は防衛費を3%に引き上げるべきだ」と主張している。
こうした文脈で見た時、シンガポール人研究者が発した質問は、少しも突拍子なものではない。この問いに対し、私は主語を日本政府と自分とに分けて答えた。
〈同盟解消は絶対に困る~政府の場合〉
日本政府ならどうするだろう? もちろん、実際にそんなことを言われたら、政府は〈3%にまで行かない水準の防衛費増で矛を収めてもらう〉よう交渉するだろう。しかし、トランプが一切の妥協に応じず、「3%か、同盟解消か」の〈二者択一〉を迫られた場合には、どんなことをしてでも防衛費をGDP比3%に引き上げ、日米同盟を維持することが政府の選択となるに違いない。政治家や官僚の大多数は、「日米同盟を維持すること以上の国益はない」という考え方に染まっている。〈同盟解消〉という選択肢は最初から排除される。
参考までにざっと試算してみると、日本が2027年度に防衛費をGDP比3%にするためには、ざっと8兆円の追加支出が毎年必要になる。(現在政府がそうしているように〈2022年度の〉GDP比3%でよければ、追加支出は5.5兆円程度となろう。[5] )仮にその全額を消費税で賄えば、「3%+α」の増税が必要になる。今日の弱い政府にそんなことはできないので、結局は国債増発に走って将来にツケを回す可能性が高い。
〈そこまで言うなら、なくてもよい~私の答〉
では、私ならどうか? 「どうぞ、解消してください」と言う、が答であった。国の防衛をないがしろにしていい、という意味ではない。専守防衛能力を充実させることは必要不可欠だ。しかし、経済の停滞が続いて財政状況が好転する望みのない中、防衛費ばかりを大々的に増やし、教育・技術開発・人口減少対策等、総合的国力の礎となる分野に十分な予算を回せない日本の現状は、国家戦略として〈本末転倒〉している。ましてや、GDP比3%という今以上の防衛費偏重の予算構造を受け入れれば、日本経済は将来にわたって再起の芽を摘まれてしまう。日米同盟残って国滅ぶ--。そんな状況を強制されるくらいなら、日米同盟は解消した方がよい。
唯一、日本が今以上に防衛費を増強することが正当化されることがあるとすれば、中国が(ウクライナへ侵攻した)ロシアのような国になり、日本を侵略する可能性が差し迫っている場合である。しかし、実際の中国はロシアとは違う。その点に関しては、今回会ったシンガポール人学者たちも皆、私と同意見だった。「今日のウクライナは明日の東アジア(台湾)」という見方もしていない。
したがって、防衛費をGDP比3%に増やせという要求は呑めない、という結論は変わらない。
日米同盟を解消したら、日本はどうする?
前節で紹介した質問に「私なら、日米同盟を解消してもよい」と答えたところ、シンガポール人学者は間髪入れず、「日米同盟を解消した場合、日本は安全保障戦略をどうするのか?」と訊いてきた。
私は「ああ答えたら、こう聞いてくるわな」と内心苦笑いした。「日本は対米自立すべきだ」と日頃言いながらも、私はこれまで「日米安保を解消すべきだ」とまで主張したことはない。だから、「日米安保なしに日本の外交安全保障をどうするのか」について、具体的に考えたことがなかった。
と言うわけで、私は即興でこの質問に答えた。それだけでは舌足らずな部分もあるので、本稿では少し肉付けしたものを以下に記す。[6]
〈日中同盟×〉
日米安保条約を解消した時、同盟の組み替えを考えるのであれば、「日中同盟」という選択肢になる。だが、これは現実的にも政治的にも考えにくい。
日米同盟を解消したからと言って、中国が日本に対して優しくなったり、日中間の懸案がなくなったりするような事態は、残念ながら起きない。日本国民の多数派が中国に対してかつてのような親近感を抱くことも期待できない。同盟を結ぶなど、論外であろう。
中国の方も、日本と同盟を結ぶ考えは持たないだろう。中国という国は攻守同盟の締結に極めて慎重な国である。現在、中国が公式に相互防衛条約を結んでいるのは北朝鮮だけ。それですら、「米朝が今日戦っても中国が約70年前のように米国と戦うとは限らない」と言われている。中国軍をウクライナ戦線へ派兵していないことからもわかるとおり、中国はロシアとの間で攻守同盟を結ぶことにも消極的だ。
そもそも論としても、日中同盟は成立不能である。つまり、〈共通の敵〉が存在しないのだ。日米安保条約を解消したとしても、日本は米国による軍事侵攻を心配しない。中国も台湾独立以外の局面で米国と戦う意志は皆無だ。その台湾有事で米中が万一戦争に及んだ時、日本は中国側に立って米国と戦うのか? 悪い冗談である。
〈アジア版NATO×〉
バイ(2国間)の同盟でなければ、石破茂総理が思いつきで述べた「アジア版NATO」はどうか? これもやはり、リアリティがない。
第1に、アジア版NATOのような集団防衛機構を創設して参加しようと思えば、日本は憲法を改正し、集団的自衛権を無制限に認める必要がある。(改憲論者はこの点を問題にしないであろうが…。)
第2に、中国を対象にするのであれば、米国が入っていないと軍事的には「張り子の虎」である。しかし、日米同盟を解消しておいて、米国にアジア版NATOで指導的役割を発揮してくれ、と頼むのは支離滅裂。それでなくても、今日の米国はマルチの仕組みで自らの手足を縛られることを嫌う。米国からは相手にされない公算が大きい。それでも頼み込むのであれば、日本は「防衛費をGDP比3%に増額する」ことを含め、今トランプから求められている以上の対米譲歩を自ら繰り出す羽目に陥る。
第3に、中国を暗黙の仮想敵にするアジア版NATOの創設に日本が動けば、中国との対立は激化せざるを得ない。韓国や東南アジア諸国を含め、誰もそんな組織に加盟しようとはしない。[7] 日米同盟を解消した日本が一人ぼっちで中国に喧嘩を吹っかける構図は漫画そのものである。
〈中立×〉
同盟(集団防衛)が無理なら、中立はどうか? 言うだけなら簡単だが、単に中立を宣言するだけでは、安全保障は担保されない。しかし、日本のような規模の国(=小国ではない)がスイスのように条約で関係国から安全と独立の保障を取り付けようとしても、実現可能性は極めて低い。米中対立の情勢下では、なおさらそうである。
〈したたかな自然体〉
では、日米同盟を解消した日本に道はないのか? そうとも言えない。現に、どの国とも安全保障条約を結ばず、さりとて中立でもない国はたくさんある。
米国と安全保障条約を締結している同盟国は、NATOと米州機構(OAS)のほか、オーストラリア、ニュージーランド、日本、韓国、フィリピン。[8] 加えて、条約は結んでいないが、イスラエルも日本以上の同盟国である。[9] 逆の角度から見ると、それ以外の国々は、米国と安全保障条約を結んでいない。だが、そうした国々も、大半は戦火に見舞われるでもなく、しっかり存立している。
防衛政策を「条約に基づく同盟か、中立か」の単純な二分法で説明できる国はむしろ少ない。例えば、シンガポールは米国と安全保障条約を結んでいないが、米軍による自国施設の使用や領土の通過を認め、軍同士の共同訓練等も行っている。米国にとってシンガポールは準同盟国またはパートナー国という位置付けだが、条約上の防衛義務は当然ない。核の傘も提供していない。しかし、だからと言って、シンガポールは米国と条約上の同盟関係に入ることを望んでなどいない。米国も中国も選ばないことが安全保障上、最も都合がよいと計算しているためだ。
日米同盟を解消するのであれば、日本もそれくらいの〈割り切り〉が必要である。日米安保条約の下で(錯覚も含めて)享受していたような安心感は確かになくなる。しかし、米国の庇護を捨てて困難や不透明性に直面した時、自助の精神を取り戻した日本は、外交力と防衛力を駆使して必ずや対応することができる。
例えば、日米同盟を解消した後、もしも中国が日本に圧迫を加えてきたら、シンガポールが米国に供与しているような〈新しい日米安保協定〉を結びなおしてもよい。もちろん、現在の日米安保とは質的に異なるものとすべきだ。日本列島の地理的な位置や自衛隊の能力は、米国にとって戦略的価値が非常に高い。政府がよほど無能でない限り、ディールは可能であろう。上記をカードにして中国と渡り合うことも考えられる。
おわりに
トランプによる〈一方的な保護関税[10] 〉の洗礼を受け、日本では「いかにトランプを宥めて、ダメージを減らせるか?」という議論が引きも切らない。政治の表舞台やメディアから聞こえてくるのは、「トランプの要求はディールの一環だから、どこかで軟着陸できる」「トランプのやり方はいずれ破綻するから、矛を収めてくる」「トランプは中国との対抗を念頭に置いているので、最終的には日本に配慮するはず」という希望的観測ばかり。「対米依存を見直せ!」という声は寡聞にして知らない。日本社会の底流に流れているのは、「日米同盟は日本の命綱だから、やり過ごすしかない」という諦観なのだと思えてならない。
でも世界的に見た時、それは決して〈当たり前〉の反応ではない。私がシンガポールで会った研究者たちの中には、「米国が変わったのだから、自分たちもそれに適応して変わらなければならない。米国に従ってばかりでは駄目だ」と言う者が少なくなかった。(誤解のないよう一言付け加えておく。彼らは決して、米国の代わりに中国と組もうとは考えていない。「米中のいずれも選ばない」という姿勢はトランプ登場後も一貫している。)
今回、シンガポールという異国の地で日本の常識とは異なる意見に接したことによって、「日米同盟を否定してはならない」という固定観念は私の頭の中から消えた。今後は、「日米同盟を維持・強化する」という呪文から自らを解き放ち、あらゆる選択肢を俎上に載せて日本の国家戦略を論じたいと思う。
詰めるべき点は多い。空想的平和主義に基づく対米自立論では、国際政治の荒波の前に一瞬にして崩れ去るだろう。軍事的リアリズムに立脚した外交力をいかに取り戻すか? AVPで議論を深めていく所存である。
---------------------------
[1] » 「トランプ以降の米国」と日本の針路 Alternative Viewpoint 第76号|一般財団法人 東アジア共同体研究所
[2] トランプ次期大統領 “NATO加盟国 GDPに占める国防費5%に” | NHK | トランプ次期大統領
[3] トランプ氏、日本に米軍の駐留経費負担4倍増を要求=米外交誌 | ロイター
[4] トランプ氏、日米安保条約に再び不満示す 「日本は何も支払わない」 [トランプ再来]:朝日新聞
[5] 日本の「防衛費=GDP比2%」のカラクリについては、下記参照。 » 2027年度の防衛費はGDP比2%に届かない 「Alternative Viewpoint」第75号|一般財団法人 東アジア共同体研究所
[6] シンガポール人学者の質問に対する実際の回答では、日中同盟と本稿で「したたかな自然体」と形容した議論を中心にした。
[7] 米国が参加すれば、フィリピンもアジア版NATOに興味を示す可能性はある。だが、それ以上に広がることはない。
[8] ただし、OASにおける米国の防衛義務は形骸化しているのが実情である。
[9] 湾岸諸国との関係を考慮し、米国はイスラエルとの間で相互防衛条約を締結して来なかった。ただし、2019年にトランプ大統領はイスラエルと相互防衛条約の締結について協議したと述べたことがある。米イスラエル首脳、相互防衛条約を協議 – 日本経済新聞
[10] トランプ政権は「相互関税」という言葉を使い、日本のメディアもそれを踏襲している。しかし、米国政府が何と言おうと、トランプ関税は古典的な保護主義に基づく一方的なものだ。また、相手に都合のよい言葉をそのまま使うこと自体、相手のペースで交渉することを意味している。私はトランプに迎合して「相互関税」という言葉を使うことを拒否する。