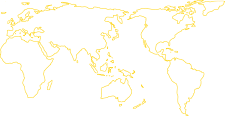2025年8月20日
はじめに
今年は戦後80年である。終戦から50年(1995年、村山富市総理)、60年(2005年、小泉純一郎総理)、70年(2015年、安倍晋三総理)と日本政府は節目毎の終戦記念日に内閣総理大臣談話(以下、終戦談話)を発出してきた。[1] しかし、今回は自民党内を含めた右派の猛反対によって総理談話という形式は早々に潰え、石破茂総理が〈個人的見解〉という形であっても何らかの文書を出すか否かに注目が集まった。結局、8月15日に石破が見解を出すことはなかった。[2]
一方、米国ではトランプ大統領が8月14日に第二次世界大戦勝利80周年のメッセージを発し、英国もチャールズ国王が終戦記念日80周年の音声メッセージを発表した。[3] 中国は抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年記念式典を9月に行うので、その時には当然メッセージを出す。また、日本と同じ敗戦国のドイツでは、5月8日にシュタインマイヤー大統領が議会演説を行い、ドイツ人が「犯罪的な戦争を引き起こし、ヨーロッパ全体を奈落の底に引きずり込んだ」と率直に認めた。[4] 国際的に見た時、石破が終戦談話を出せなかったことは、汗顔の至りと言うほかない。
それでも、石破は全国戦没者追悼式の式辞(以下、追悼式辞)で「進む道を二度と間違えない。あの戦争の反省と教訓を、今改めて深く胸に刻まねばならない」と述べた。[5] 総理大臣が追悼式で「反省」という言葉を使ったのは、民主党政権(野田内閣)以来、実に13年ぶりだと言う。右派に対する石破のせめてもの抵抗なのであろう。
石破が「反省」を口にしたことは、安倍・菅・岸田時代に比べれば〈小さな前進〉ではある。だが、この二文字の有無だけを議論しても無意味だ。本当に大事なことは、何をどう反省し、いかなる教訓を導き出したか、であろう。
今回、歴代内閣の文書や発言に改めて当たってみたのだが、「反省」や「教訓」という言葉以前の問題として、「政府はあの戦争の何が間違っていたと総括しているのか」がほとんど伝わってこないことに私は愕然とした。同時に、政府や各党が「不戦の誓い」や「恒久平和」等を口にしても、どこか空虚に感じられる理由もそこにある、と得心した。
AVP本号では、これまでに出された終戦談話、追悼式辞、および今年の終戦記念日に主要政党が出した談話等を素材にして、政府ひいては日本人の戦争に対する総括を紐解く。[6]
1. 多大な惨禍をもたらした
厚生労働省によれば、日中戦争(1937年7月~)以降、終戦までの間に内外で亡くなった軍人・軍属(約230万人)と民間人(約80万人)の合計は約310万人。[7] これはロシア・ウクライナ戦争で今年4月末までに亡くなった人数(ロシア=約20~25万人、ウクライナ=約6~10万人)をも大きく上回る。[8] また、日本の加害や戦争行為に伴う死者数は、中国や東南アジア、米国等で少なくとも数百万人、資料によっては2千万人を超える。
こうした被害について、村山終戦談話は「国民を存亡の危機に陥れ」、「多くの国々に多大の損害と苦痛を与え」たと述べた。小泉談話は「悲惨な戦争」、安倍談話は「戦争の惨禍」と呼んだ。先の大戦がもたらした人的・物的な被害はあまりに甚大であり、いかなる理由によっても正当化できない。それを裏返せば、先の大戦はあまりに多大な惨禍をもたらしたが故に間違っていた、という論理が導かれる。当然と言えば当然のことだが、そこには問題も潜む。
第1に、日本の外の被害には目を瞑る風潮が強まりつつある。村山談話と小泉談話では、日本がアジアをはじめとする諸外国に多大な損害と苦痛を与えたことが明記されていた。しかし、安倍の70年談話になると、諸外国の損害と苦痛について触れられてはいるが、日本が加害の主体であることが曖昧になった。
追悼式辞においても、民主党政権以前の総理大臣は、2007年の安倍や麻生を含め、「多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えた」旨のことを述べていた。[9] だが2013年の安倍以降、この種の言及はカットされるようになる。石破も触れなかった。
他国の被害に触れない傾向は、主要政党が出す終戦談話で一層はっきりと見て取れる。自民党、国民民主党、日本維新の会、参政党が今年8月15日に出した談話等は日本が他国に被害を与えたことへの言及がない。[10]
第2の問題は、先の大戦ほどのひどい被害でなければ、戦争はしてもよい、という考え方も可能になることだ。他国の被害を無視する傾向と合わせれば、「日本に対する被害がある程度にとどまるのであれば、戦争もやむを得ない」と考える人も出てきかねない。
2005年の小泉談話は「二度と我が国が戦争への道を歩んではならない」と述べていた。2015年の安倍談話では、「二度と戦争の惨禍を繰り返してはならない」へと変わった。今年、石破が追悼式辞で読んだのも、「戦争の惨禍を決して繰り返さない」であった。考えすぎかもしれないが、この微妙な変化が私には引っかかる。
2. 侵略戦争を行った
1928年に締結されたパリ不戦条約は自衛目的以外の戦争を違法化したと言われるが、日本もこれに署名し、批准していた。それを受け、先の大戦は侵略戦争なので駄目だった、という総括もよく耳にする。村山の終戦談話は、「わが国は、遠くない過去の一時期、国策を誤り、戦争への道を歩んで国民を存亡の危機に陥れ、植民地支配と侵略によって、多くの国々、とりわけアジア諸国の人々に対して多大の損害と苦痛を与えました」と率直に述べ、(日中戦争やアジア諸国での戦争が)侵略戦争であることを認めた。小泉談話もその基本線を継承した。
ただし、戦前・戦中の日本が侵略と植民地支配を行ったという認識は時間の経過とともに曖昧化し、それを否定したい人々が増えた。安倍の終戦談話にも「植民地支配」や「侵略」という言葉は出てくるが、その主体が日本であったことは巧妙にぼかされている。
日本がアジア諸国への侵略と植民地支配を認めたくないという風潮は、政党レベルでも明白に表れる。主要政党のうち、今年の終戦記念日に発出した談話等で日本の侵略や植民地支配に触れたのは、立憲民主党、日本共産党、れいわ新選組のみだ。[11]
さて、安倍の終戦談話(2015年)は「いかなる武力の威嚇や行使も、国際紛争を解決する手段としては、もう二度と用いてはならない」と宣言した。日本の戦前・戦中の行為を侵略とみなすか否かに立場の違いはあるかもしれないが、政府や諸政党は、侵略戦争は言わずもがな、自衛以外の戦争は行わない、という点では大方一致しているだろう。[12]
だが、それが戦争の歯止めになると安心するのは早計だ。不戦条約以降も今日まで、自衛を理由にして数多の戦争が行われてきた。日本の対米英戦争も「自存と自衛」のために行われたと言うのが建前であった。[13] 最近も、プーチン大統領はウクライナ侵攻を正当化するため、自衛権の行使(米欧に対する個別的自衛権とドネツク・ルガンスク人民共和国からの要請に基づく集団的自衛権)を持ち出した。[14]
あくまで可能性の話として述べるのだが、台湾有事についても、その起こり方にかかわらず、日本が自衛権の行使として中国と戦うシナリオはあり得る。国家承認していない台湾に対して集団的自衛権を適用できるかという問題は残るものの、米国が軍事介入すれば、米国を対象にした集団的自衛権(存立危機事態)は成立しうる。また、米中間で戦闘がある程度激化すれば、在日米軍基地等が攻撃される可能性が高い。そうなれば、個別的自衛権(武力攻撃事態)を発動できる。
「侵略戦争は駄目」から始まって「自衛戦争ならよい」という単純な議論に陥れば、先の大戦からなんの教訓も得ていない、と先人に笑われよう。
3. 国際秩序に挑戦した
前節において、安倍の終戦談話では戦前の日本の行為が侵略であったことが曖昧になった、と指摘した。だが興味深いことに、安倍はそれとは別の観点から戦前の日本を批判している。曰く、「満州事変、そして国際連盟からの脱退。日本は、次第に、国際社会が(第一次世界大戦の )壮絶な犠牲の上に築こうとした『新しい国際秩序』への『挑戦者』となっていった。進むべき針路を誤り、戦争への道を進んで行きました(括弧内は筆者註)」。そして、「国際秩序への挑戦者となってしまった過去を、この胸に刻み」、「自由、民主主義、人権といった基本的価値を揺るぎないものとして堅持し、その価値を共有する国々と手を携えて、『積極的平和主義』の旗を高く掲げ、世界の平和と繁栄にこれまで以上に貢献してまいります」と宣言したのであった。
実際には、安倍の言う「新しい国際秩序」は、第二次世界大戦を経て勝者である米国が中心になって作られたものである。戦前の世界では米国も国際連盟に参加しておらず、「新しい国際秩序」への確たる胎動があったわけではない。安倍の解釈は〈後付け〉と言うべきものだ。
そのうえで言えば、安倍がこの視点を持ち出してきたことは、日本政府が価値観外交を主張し、日米で中国に対抗しようとする姿勢を強めたという文脈で理解する必要がある。戦前は〈新しい国際秩序に挑戦した悪者=日本〉だったが、現在は〈民主主義や法の支配に基づく日米欧主導の国際秩序に挑戦する悪者=中国・ロシア〉という構図を暗黙裡に示唆しているわけだ。
価値観に基づく外交安全保障というものは、一見格好がよい。だが実際には、それによって関係国間の対立が不必要に煽られ、危機を増幅させることが少なくない。例えば、民主主義や法の支配に基づく国際秩序を守ることを大義名分にして日米が台湾に肩入れすれば、台湾の独立志向や中国の疑心暗鬼が強まる結果、起こらなくてもよい台湾有事を誘発しかねない。「民主主義 対 権威主義」を含め、価値観に基づく二分法にはくれぐれも用心したい。
4. 勝ち目のない戦争をした
日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦は、日本が(少なくとも一応は)勝利した。そのため、〈過ち〉ではなく〈成功例〉と受け止められることが多い。逆に、先の大戦は負けた――しかも、大負けをした――が故に〈間違い〉となった面が否定できない。「日本は国力差を無視して戦争を始め、負けるべくして負けた」という良識派軍人の悲憤は回顧録や映画・テレビ番組等を通してよく知られている。
ところが不思議なことに、政府や各党の談話等には、「勝てるわけのない無謀な戦争をした」という批判を直接述べたものがあまりない。ざっと見たところでは、2010年の終戦記念日に出された自民党の談話が「連合国との間に圧倒的な国力の差が存在していたにもかかわらず、何故開戦に至り、中途の講和も成らず、祖国が焦土と化し、尊い幾多の人命が失われたかについても、正確な認識を持つことが必要と考えます」と述べているくらいだ。[15]
国家指導者や戦略家にとって、勝つ見込みのない戦いを仕掛けることは最も忌むべきことの一つである。しかし、過去を振り返る分には何とでも言えるが、歴史の現在進行形の場に立ち会ったとき、勝ち負けの見込みを正しく立てることは必ずしも易しいことではない。例えば、戦争が始まってから3年以上が経過してもウクライナを降伏させられないという事態は、2022年2月にウクライナへ侵攻する前のプーチンには想像もできなかっただろう。2023年10月にイスラエルを急襲する前のハマスも、イスラエルが今日までジェノサイドとも呼ぶべき攻撃を継続しているとは予想しなかったはずだ。
対米戦を始める前の日本にしても、表面的には「戦争に負けない」ことになっていた。企画院や陸海軍内では国力的に戦争継続は不可能だという報告書が作成されていたが、開戦派の圧力によって数字が辻褄合わせされたのである。[16] そして、人間は追い込まれると自分に都合のよいシナリオにすがりつく。「ドイツが米国に勝利する」という希望的観測や「短期決戦で米艦隊を撃滅して講和に持ち込む(山本五十六)」という構想もその例だ。[17] もちろん、今から見れば、何れも〈おめでたい〉としか言いようがない。
くどいようだが、「負ける戦争はしない」という観点から再び台湾有事について考えてみよう。中台間で軍事衝突が起きても、米国が軍事介入しなければ、右の人たちを含めても「台湾を守るため、日本は単独でも中国と戦おう」と言う人はおるまい。日本の敗北は必至だからである。だが、米国が軍事介入する場合はどうか? (十分に)勝ち目があるとみて「米国と共に戦え」という声も出てこよう。
だが、ここで本当に重要なのは、単純な勝ち負けではない。日米と中国が戦えば、本州を含めた日本の全域が中国のミサイル攻撃を受けることを覚悟せざるを得ない。(反撃能力でそれを抑止できるという説明は詐欺的な虚偽である。)皮肉なことに、戦局が米国に有利に進んだ方が、中国による対日攻撃は激化する可能性が高い。追い込まれた中国は、米軍の主な出撃拠点にして兵站基地でもある日本を叩こうと必死になるためだ。加えて、米中は共に核保有国である。核兵器か使われるという最悪の想定もしておかなければならない。いずれにせよ、日米が勝利し、中国の台湾侵攻が阻止されたとしても、多くの日本人の生命と財産が奪われたのでは、まったく報われない。
終わりに
以上、日本が先の大戦をどう総括しているのか、私の想像で補いながら分析してみた。日本は本当に真剣に戦争を総括したことなどない、というのが率直な感想だ。先の戦争の何が間違いだったのか、考えた振りはしているものの、踏み込みが全然足りていない。勢い、反省も教訓も〈通り一遍〉なものとならざるを得ない。
今日、日本では「抑止力を高めて戦争を未然に防ぐ」という議論が何の抵抗もなく受け入れられている。専守防衛の充実・強化は確かに不可欠ではある。だが、力(軍備増強)による解決にしか目を向けないのでは、戦前の過ちを繰り返す可能性が高い。終戦80年を迎えた現在、将来の戦争を避けるためにも、我々は謙虚かつ現実的な姿勢で自らの過去を振り返りたい。
===============================================
[1] 村山総理大臣談話
小泉内閣総理大臣の談話
平成27年8月14日 内閣総理大臣談話 | 平成27年 | 総理の指示・談話など | 総理大臣 | 首相官邸ホームページ
[2] 石破は今もなお、「戦後80年のメッセージ」を出すことに含みを持たせている。https://www.kantei.go.jp/jp/103/statement/2025/0815kaiken.html
[3] Presidential Message on the 80th Anniversary of Winning World War II – The White House
戦後80年 トランプ大統領「力による平和」の政策堅持を強調 | NHK | トランプ大統領
チャールズ国王、終戦記念日80周年にメッセージ
「戦争の悲劇」今日も 英国王、対日勝利80年でメッセージ:時事ドットコム
[4] Der Bundespräsident – Speeches – “We are all children of 8 May” (日本メディアが伝える本演説の内容には偏りがあるため、興味のある方は翻訳ソフトを使われた方がよい。)
[5] 令和7年8月15日 令和7年度全国戦没者追悼式総理大臣式辞 | 総理の演説・記者会見など | 首相官邸ホームページ
[6] 本稿で総括するのは「1945年8月15日に日本の敗戦を以って終わった戦争」、終戦記念日の談話等では「先の大戦」と呼ばれるものについてである。「先の大戦」という呼称問題についても思うところはたくさんあるが、今回は控えておく。
[8] ロシア・ウクライナ 被害の大きさ 物語る死傷者数(辻’s ANGLE) – 国際報道 2025 – NHK
[10] 終戦記念日にあたって 党声明 | 党声明 | ニュース | 自由民主党
戦後80年の終戦の日にあたって(談話) | 新・国民民主党 – つくろう、新しい答え。
【戦没者を追悼し平和を祈念する日】吉村洋文代表による談話発表のお知らせ|ニュース|活動情報|日本維新の会
参政党 -sanseito- | 参政党 終戦80年談話
[11] 【代表談話】80年目の終戦記念日にあたって – 立憲民主党
戦後80年にあたって | 日本共産党
【声明】80回目の敗戦の日を迎えて(れいわ新選組 2025年8月15日) – れいわ新選組
なお、日本保守党の長い談話には「侵略」や「植民地支配」という言葉がしっかり出てくる。だが、それらが使われているのは、日本が侵略や植民地支配を行ったことを認め、反省するのとは真逆の意味においてである。戦後八十年に寄せて《談話》 – 日本保守党|日本を豊かに、強く。
[12] 国際法上は国際連合によって正当化された武力行使も認められる。
[13] 1941年の対米英開戦の詔書には以下の文言がある。「米英両国は、残る政権(蔣介石政権、重慶国民政府)を支援し、東アジアの戦禍と混乱を助長し、平和の美名にかくれて、東洋を征服する非道なるたくらみをたくましくしている。あまつさえ、くみする国を誘い、帝国の周辺において、軍備を増強し、日本に挑戦し、さらに帝国の平和的通商にあらゆる妨害を与え、ついには経済的断交をわざとおこなうことで、帝国の生存に重大なる脅威を加えている。(中略)米英は、少しも譲り合いの精神を持たずに、むやみに事態の解決を遅らせ、その間にもますます、経済上・軍事上の脅威を増大させ続け、それによってこの国を屈従させようとしている。このような事態が、そのまま続いてしまったならば、東アジアの安定に関して、帝国による積年の努力は、ことごとく水の泡となり、帝国の存立も、まさに危機に瀕することになる。ことここに至っては、帝国は今や、自存と自衛のために、決然と立ち上がり、すべての障害を打ち砕く以外に道はない。」 日本の対米英宣戦布告 – Wikipedia
[14] 和仁 健太郎「ロシアによるウクライナ軍事侵攻の合法性と国際社会の対応」 710-2
[15] 生真面目な谷垣禎一総裁(当時)の面目躍如と言った一文である。 終戦記念日にあたって 総裁談話(8/15) | 党声明 | ニュース | 自由民主党
[16] 日米開戦の決意 国力判断をゆがめた企画院の数字合わせ : 読売新聞
[17] 山本五十六が日米戦の回避を求めた理由 説明努力を怠り敗北 : 読売新聞 仮に日本軍がミッドウェー海戦に勝利していたとしても、米国が講和に応じることはあり得なかった。「やられればやられるほど徹底的にやり返す」というのが米国の本質なのである。