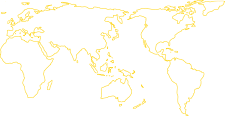2025年4月30日
はじめに
去る4月14日と15日、シンガポールへ行き、中国外文局、清華大学、南洋理工大学が共催する『Think Asia Forum』という会議に出席してきた。AVP本号では、この会議で私が発言した内容をかいつまんで紹介する。ベースとなるのは「変化する世界におけるアジアの未来」というセッションで行ったプレゼンテーション。それに他のセッションで述べたことを加えるなど適宜編集を行い、スピーチ仕立てにしたものが本稿である。
===========================================
変化する世界と日本の行方
21世紀の今日、我々の住む世界は「不均等な多極化(uneven multipolarity)」と呼ぶべき状況にあります。米国民の多数が「米国は寛容な世界的指導者であることをやめるべきだ」と主張するドナルド・トランプを大統領に選んだのは、この「不均等な多極化」に対する彼らなりの対応と考えることもできましょう。
トランプ2.0を受け、米国と対立する国々だけでなく、米国の同盟国も国家戦略の見直しを迫られています。欧州では、独自の防衛力を構築して米国からの自立を模索する動きも見られます。日本はどう対応するのでしょうか?
日米同盟:コスト・ベネフィットの変化
第2次世界大戦後、日本は対米同盟を外交防衛戦略の要と位置付けてきました。その選択は日本に外交的自主性の喪失を強いる一方で、終戦後暫くの間は〈自国防衛に費やす予算を最小限に抑え、経済復興に専念する〉という意味で合理性を持っていました。そして何よりも、冷戦期はソ連、最近は中国や北朝鮮の脅威に備えるという抑止・防衛的な意義が日米同盟に期待される最大の有用性と考えられてきました。こうして、多くの日本人にとって日米同盟の維持・強化は疑うべくもない国策となったのです。
でも今、その〈自明の理〉が大きく揺らぎ始めています。日本は近年、自ら防衛予算を大幅に増加させるようになりました。米国は今後、防衛予算のさらなる増額、米軍駐留経費の負担拡大、自衛隊の役割拡大を日本に要求してくるでしょう。また、トランプ関税は、日本が同盟の優等生として振る舞ったとしても、貿易・投資の面で米国が日本を優遇しないことをはっきりと示しました。日米同盟はもはや、「安上がり」ではありません。
同盟の最大の眼目であった抑止・防衛効果についてですらも、米国をどこまで当てにできるかは不明瞭です。ロシアがウクライナに侵攻した時、バイデン大統領(当時)は「米軍を送ってロシアと戦うことはない」と即座に明言しました。トランプ大統領も「ロシアが攻めてきてもNATO加盟国を守るとは限らない」と言ってのけました。北大西洋条約は日米安保条約に比べて共同防衛の縛りがはっきりしているにもかかわらず、この有り様なのです。
短期では米国にしがみつくが、中長期では自立を模索
それでは、日本は欧州のように戦略的自立性を強めようとするでしょうか? 答はそれほど単純ではありません。
何よりも日本には、対米依存を減らしてもやっていけるだけの国力が圧倒的に不足しています。そのうえ、日本は〈集合的な対応〉をするための仲間を持っていないのです。
欧州と比較してみましょう。ドイツやフランスと言った欧州の中堅国も、1国で米国からの戦略的自立性を追求することはできません。しかし、ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によれば、欧州のNATO加盟国の2024年の軍事支出を合計すれば、4540億ドルに達します。[1] これはロシアの1490億ドルを凌駕する水準です。[2] 欧州がまとまれば、対米自立の実現は、簡単ではないにせよ、まったく不可能な話とは言えません。
一方で、日本の軍事支出は、2027年で750億ドル前後になります。[3] これは同年の日本のGDPの1.75%程度、2022年度のGDP対比では2%に相当します。仮定の話であり、実際には財政的に不可能だと思いますが、この数字をGDP比3%まで上げたとすれば、日本の防衛費は1280億ドル程度となるはずです。しかし、中国は2024年時点で年間3100億ドル以上を軍事に費やしています。この数字は今後さらに増加することが確実です。自衛隊のマンパワーや防衛産業基盤の面でも、日本の能力は中国に大きく見劣りしています。日本単独で中国に伍すことは、率直に言って厳しいと言わざるを得ません。では、日本はEUのようにまとまって対抗できるでしょうか? 周囲を見渡しても、そのようなパートナー国は1つも見当たりません。
もう1つ、自立を阻む要素があります。日本では政治家やメディアだけでなく、一般国民の間にも対中脅威論が浸透していることです。私は昨年12月に台湾を訪問しましたが、台湾の人たちよりも日本人の方が強い対中脅威認識を抱いていることに驚きました。世界で一番対中脅威認識が強い国は日本ではないか、とさえ思います。トランプが登場したからと言って、日本人の対中脅威論がそう簡単に収まることはないでしょう。自然、「寄らば大樹の陰」で米国にすがる習慣を続ける可能性は高いと思います。
以上を基に私の短期的予測を述べれば、次のとおりです。日本政府はトランプとのディールに積極的に応じ、彼の要求をできるだけディスカウントしながらも、基本的にはトランプに宥和的態度をとるでしょう。トランプがアメリカ・ファーストであるならば、日本政府は〈同盟ファースト〉なのです。
そのうえで、皆さんに強調しておきたいことがあります。それは、日本政府が採用する宥和的な政策は、効果に乏しいだけでなく、持続不可能だということです。米国の大統領は将来も、「アメリカ・ファースト」という言葉は使わなくても、従来よりも遥かに利己的であり続けます。その傾向は、民主党の大統領が誕生しても大きく変わりません。少し時間はかかっても、日本は最終的に、日米同盟の費用対効果が著しく悪化したことに気づくはずです。折にふれ、日本防衛のために米国が当てにならないと思わせられるケースも増えてきます。私の中長期的な予測は、日本は日米同盟一辺倒の路線を修正し、ヘッジを図る以外に選択肢がない、というものです。
中国、東南アジアの重視
実際に日本が対米依存を減らすためには、何が必要となるでしょうか? 私はここで2つの方針を提示したいと思います。
第1に、日本は中国との間で戦略的コミュニケーションを強化し、自らの安全保障環境を改善することに注力すべきです。目下のところ、東シナ海の問題は十分に管理可能なので、喫緊の課題は台湾情勢が悪化しないよう、危機の芽を摘むことです。例えば、日本政府は台湾独立を支持・奨励しないことをもっと明確に表明すべきでしょう。領土内に米軍基地を持つ日本が本気になれば、米国の台湾政策にも大きな影響を与えることができます。我々はそれを怖れてはなりません。
第2に、日本は戦略的に協力できるパートナー国を意図的につくる必要があります。その際、特に重要になるのが東南アジア諸国です。ほとんどのASEAN諸国と日本は、「米中の一方を選ばない」という大方針を共有しています。その意味で、東南アジア諸国は日本にとって最も有力な戦略的パートナー候補と言えます。
ただし、日本が長い間続けてきた「経済援助によって好意を得る」というアプローチは機能しなくなって久しい。[4] 日本は東南アジアに対するアプローチを根本的に変えなければなりません。例えば、日中の企業がASEAN諸国を舞台に先端技術分野で協力を進めれば、日中のみならず、東南アジア諸国の利益にもなるでしょう。まさに「ウィン・ウィン・ウィン」です。現在、日本企業の中には、米国から二次制裁を受けることを懸念し、先端技術分野で中国企業との共同開発に二の足を踏むところが少なくありません。しかし、この枠組みであれば、米国も横槍を入れにくくなるはずです。
私たちは今、歴史の大きな岐路に立っています。将来の歴史家が「トランプ2.0に対する日本の戦略的対応は〈アジアへの回帰〉であった」と振り返ることを願い、私のプレゼンを終えます。[5]
=============================================
おわりに
今、私が出席した会議でシンガポール政府の元高官が述べた言葉が強く印象に残っている。その人は「トランプ大統領によって世界はとても不透明になり、不安定化した。しかし、長い歴史を振り返れば、それこそが世界の常態である。そのような状態に置かれた時、我々が考えるべきは『まずは自らを改善せよ』ということだ。シンガポールはこれから一層、国力の強化に取り組む」と言った。要するに、〈自助〉の精神を強調したのである。
翻って、日本政府はトランプ関税への対応に大わらわである。だが、仮にトランプに関税を多少負けてもらうことができたとしても、日本企業は今後も世界の市場で売れる製品を作り続けることができるのか? 鉄鋼、電機、半導体など、20世紀後半の花形産業は軒並み衰退し、頼みの綱の自動車でさえ、EVではテスラや中国勢の後塵を拝しているのが日本経済の現実である。
目を政党に転じれば、参議院選挙対策の思惑に加え、トランプ関税への対応を名目にして、各党は給付金の交付や消費税減税というカンフル剤のバーゲンセールにいそしんでいる。しかし、減税や給付金で一時的に国民の手取りを増やしたとしても、日本経済の生産性が低いままでは、結局、給料も上がらないのでやがては手取りも減る。
日本では、企業も国民も「国に守ってもらう」ことがいつの間にか当たり前になってしまった。私は、この〈国家への依存〉が〈米国への依存〉と表裏一体のものに思えてならない。その直感が正しければ、本稿で予測したような対米自立も、この国の体質改善と表裏一体でしか進むまい。
厳しい言葉を書き連ねたが、最後に〈勇気づけられる知らせ〉も紹介しておこう。それは、トヨタ自動車が新型EVに中国・ファーウェイの基本ソフト(OS)を採用すると決め、ホンダも中国・ディープシークのAIを導入すると発表した、というニュースである。[6] 民間企業が生き残りのために清水の舞台から飛び降り、米中対立の渦中に片足を突っ込んだと言ってもよい。日本政府としては、米国が変な横やりを入れてこないよう、全力で備え、場合によっては徹底的に戦うべきだ。対米自立というのは、案外そんなところから進むような気もする。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
[1] Unprecedented rise in global military expenditure as European and Middle East spending surges | SIPRI なお、会議が開かれた時点では2024年の数字が発表されていなかったため、私のプレゼンでは2023年の数字を使用した。
[2] 国際戦略研究所(IISS)が算出した購買力平価に基づく比較では、2024年のロシアの軍事支出は4620億ドルに達し、EU加盟国+英国の軍事費をやや上回る。Global defence spending soars to new high 私も「欧州がまとまれば、ロシアに対抗して戦略的に対米自立を達成できる」と即断するつもりはない。
[3] 政府が想定する2027年度の安全保障関係経費(=約11兆円)を現行為替レートで割り、数字を丸めた。
[4] 政府は近年、ODA(政府開発援助)とは別に、SA(政府安全保障能力強化支援)という枠組みを導入した。OSAは東南アジア諸国等に対して、安全保障関連の資機材を供与したり、安保関連インフラの整備のために資金・人材協力を行ったりするものである。政府安全保障能力強化支援(OSA:Official Security Assistance)|外務省 一歩前進と言えなくもないが、〈事実上の対中囲い込み〉という日本政府の意図に各国が従うことはなさそうである。
[5] 私がシンガポールの会議で行ったプレゼンテーションと本稿は同じものではない。繰り返しになるが、念のため。
[6] 日系EVに中国の技術…トヨタはファーウェイのOS採用、ホンダはディープシークAIを導入 : 読売新聞