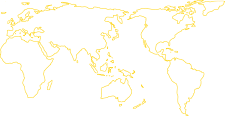2022年4月15日
はじめに
ウクライナ戦争におけるロシアの苦境を見た中国は〈自ら台湾を武力統一する〉シナリオに対して、従来以上に慎重になる--。AVPの前号(3月31日付第37号 https://www.eaci.or.jp/archives/avp/596)で私はそう論じた。では、我々は一安心してよいのか? 残念だが、逆である。中国は自らの不利を悟ったが故に、ますます軍拡路線を邁進する可能性の方が高い。しかも、米国も日本も軍拡が既定方針となりつつある。このままでは、両陣営の間で作用・反作用が繰り返され、この地域で軍拡が加速することは避けられない。AVP本号では、ロシアのウクライナ侵攻が中国の外交安全保障政策に与える影響について考察する。
台湾独立シナリオに備えよ(中国の理屈)
論理上、中国が台湾に対して武力行使に及ぶシナリオは2種類ある。
1つ目は、中国の方から積極的に台湾を武力統一するというもの。前号で述べたとおり、ウクライナでのロシアの苦戦ぶりを見た中国指導部は〈台湾の武力統一は、軍事的な成算が不確かなうえ、経済・金融制裁を含めたコストが従来想定していたよりもずっと高い〉と悟ったはずである。日米でしきりに喧伝されている武力統一シナリオだが、もともと低かった実現可能性はさらに低下した、と考えてよい。
2番目は、台湾が独立の動きを強め、それを阻止するために中国側が武力行使するというもの。中国指導部は「台湾独立を座視すれば、中国共産党による統治の正当性が根本から崩れる」と信じている。台湾独立の動きが一線を越えれば、勝敗の公算や犠牲の大小を度外視しても、台湾に武力を行使せざるを得ない。
断っておくが、予見しうる将来に台湾が独立に向けて露骨に動くことはなさそうだ。現時点で台湾の世論の大多数は現状維持を望んでいる。国立政治大学選挙研究センター(台湾)によれば、2021年12月時点で「可及的速やかな独立」を望む台湾人の比率は6%に過ぎなかった。「現状を維持しつつ、独立に向かう」という意見の持ち主は25.1%だ。一方で、「未来永劫に現状維持」が27.3%、「現状を維持し、将来のことは後で決める」が28.4%であった。[i] とは言え、世論は不変ではない。ウクライナの場合も、2012年にNATO加盟を望んだ国民は13%しかいなかったが、2014年のクリミア併合後は40%を超えるようになった。[ii] その数字は、今年2月には6割弱まで上昇している。[iii] しかも、現与党の民進党は綱領に「台湾前途の住民自決」を謳っている。米国も近年、要人による台湾訪問を活発化させたり、バイデン大統領の就任式に台湾の駐米代表を正式招待したりするなど、台湾の国際的地位の向上に前向きな姿勢を見せている。
中国としては、〈将来、台湾独立の動きを無視できなくなる〉というリスク・シナリオへの備えをやめることは絶対にできない。ところが、台湾独立を阻止するために武力行使した場合、中国側が被るであろう軍事的な被害や経済・金融制裁による損害は従来の想定よりも遥かに大きい可能性が出てきた。中国指導部が「ウクライナ戦争から教訓を学び、軍事力の更なる強化と経済・金融制裁への備えを進めなければならない」という結論に達することは、現実政治の世界では極めて自然なことである。
中国は今後、台湾有事(台湾独立阻止シナリオ)を念頭に置いてどのような動きに出るのか? 軍事、経済、外交の三分野における具体的な注目点を以下に記そう。
1. 軍事力の増強
ウクライナと台湾、ロシア軍と中国軍の違いを無視することは、もちろんできない。そのうえで言えば、AVP第37号で述べたとおり、今回のウクライナ戦争には「米軍 対 ロシア軍」の代理戦争の側面が多分にある。台湾有事を想定した時、米国の支援を受けたウクライナ軍に対してロシア軍が苦戦しているという現実は、ロシア軍の兵器体系を直接・間接的に導入している中国軍にとって他人事ではない。
近年、中国軍の能力が米軍のそれをキャッチアップし、部分的に凌駕しつつあることは事実である。今や、台湾有事で中国軍と戦えば、米軍は耐え難い犠牲を出さずにはすまないだろう。しかし、ウクライナにおけるロシア軍の惨状を見た中国は「だからと言って米軍に確実に勝てるわけではない。いや、相当の確率で敗北する可能性が高い」と兜の緒を締めているはずだ。その危機感をバネにして、中国が質量ともに軍事力強化のペースを上げることは確実である。
《軍事近代化の再加速》
軍事力増強の中身は、第5世代戦闘機、原子力潜水艦、極超音速兵器等の攻撃兵器の増強はもちろん、ドローン――攻撃のプラットフォームにも情報収集のためのセンサーにもなる――の開発配備促進、ステルス性や抗堪性の向上等、サイバー攻撃及び防御能力の強化など、広範なものとなろう。特に、AIを活用した戦闘の自動化、システム化、無人化の推進は最優先課題である。ミサイルの利用方法を含め、戦術の刷新も検討されるかもしれない。
《核軍拡》
バイデン大統領が開戦前から今日に至るまで米軍とロシア軍との直接戦闘を言下に否定し、戦闘機等をウクライナへ供与していないのは、ロシアが強大な核戦力(核弾頭及び運搬手段=爆撃機、地上発射・潜水艦発射ミサイル)を保有しているためだ。ストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の推計では、2021年1月時点で米国が5,550発の核弾頭を保有するのに対し、ロシアは6,255発を有している。[iv] ウクライナ戦争は核兵器が絶大な対米抑止力を持つことを世界に知らしめた。
SIPRIによれば、同時期に中国が保有する核弾頭数は350発である。ウクライナ戦争で核戦力の有効性が再評価された今、中国も台湾有事において米軍を抑止するために核戦力を大幅に強化すべきだと考えるに違いない。昨年11月に米国防総省が議会宛に提出した年次報告書は、中国が2027年までに核弾頭数の実戦配備数を700発まで増やす能力を持つと述べ、2030年までに保有する核弾頭数を少なくとも1,000発まで増やしそうだと予測している。[v] 中国が南シナ海に基地を建設しているのも、米軍から核の第一撃を受けた場合に潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)を残存させ、太平洋に展開させる能力を改善することが最大の理由である。中国が従来を大幅に上回るペースで核弾頭数を増やし、ICBMやSLBMなど運搬手段の近代化を加速することになれば、東アジアの緊張はいやが上にも高まる。
《軍事支出増》
中国軍の実力が米軍に対してまだ不十分だと思い、一層の軍事近代化を進めるということになれば、当然のことながら中国は今後、軍事予算増額のペースをギアアップするだろう。しかも、今後は米国、日本、欧州など世界中で軍事予算を増額する潮流がはっきり見受けられる。中国も従来ペースの軍事予算増では安心できなくなるだろう。米日欧などとの間で作用・反作用が働き、軍事支出の面でも軍拡競争が起きることは必至だ。

(SIPRI-Milex-data-1949-2020_0.xlsx (live.com) から作成)
上記の元ベースのグラフでも明らかなとおり、中国の軍事予算増は今に始まったことではない。年額の軍事支出で見た時、中国の軍事予算(米ドル換算、2020年)は2,523億ドルに達し、世界第2位の軍事大国である。[vi] これは日本の防衛予算(ドル換算で491億ドル)の5倍以上にあたる。[vii] 一方で、目を転じて米国の軍事費(7,782億ドル、2020年)と比較すれば、3分の1弱の水準にとどまる。地球規模に展開する米軍に対し、中国軍の活動範囲はずっと狭い。それでも、下のグラフを見れば、米中間に存在する格差はやはり印象的だ。増減の波はあるものの、米国の軍事支出増加ペースも十分にすさまじい。

(SIPRI-Milex-data-1949-2020_0.xlsx (live.com) から作成)
意外に思えるだろうが、中国の軍事費の対GDP比は過去20年間近くの間、少なくとも公表ベースでは2%を切っており、どちらかと言えば低下傾向にあった。2020年の数字は1.7%だったが、これは米国(3.7%)やロシア(4.3%)よりもずっと低い。[viii] にもかかわらず、中国は経済成長率が他国よりも段違いに高かったため、軍事費の伸び率は米国等を凌駕してきたのである。軍事費の対GDP比が低いということは、その気になれば中国には軍事費をもっと増加させる余力がある、ということだ。近年、中国経済は明らかに成長鈍化局面に入った。一方で、上述のとおり、軍事費は一層増やす必要がある。結果的に今後は中国も軍事費の対GDP比を徐々に引き上げていくことになるだろう。
2. 経済自立性をいかに高めるか?
ウクライナ戦争を見た中国は、台湾有事が起きた場合の米国との戦いは、軍事面のみならず経済面も含めた総力戦となることを痛感しているに違いない。仮に軍事面で台湾(米国)側を圧倒して独立を断念させることができたとしても、今日ロシアが受けているような広範な経済・金融制裁を西側諸国から継続的に受けたら、中国経済は大幅なマイナス成長に陥ることが確実である。今日の豊かになった中国人が経済的な不自由にどの程度耐えられ、中国共産党の統治に対する不満を表面化させないで済むかも予断を許さない。中国共産党指導部にとって〈西側による経済制裁を受けても体制の動揺をきたさない程度に経済的自立性を高める〉ことは、避けて通れない課題になったと考えられる。
中国の経済規模や貿易量はロシアとは比較にならないほど巨大だ。中国のGDP(2020年、世銀)は 14兆7千億ドルとロシア(1兆5千億ドル弱)の約10倍。米中貿易(2021年、米国勢調査局)は6,570億ドルであり、米露貿易(360億ドル)の18倍に達する。いわゆる「西側」が中国に経済・金融制裁をかけた時の〈返り血〉も遥かに多くなる。しかし、今回のウクライナ戦争では、米国やウクライナ側が行った国際世論工作(広義の情報戦)の成果もあって、西側では「民主主義や人権を守るためなら、経済的なコストがかかっても制裁に踏み切るべき」という思潮が一気に強まった。中国指導部も「中国経済は巨大だから本格的な経済・金融経済はできない」と高を括って済ませるわけにはいかないはずだ。
《双循環》
経済自立性を高めるという方針自体は、習近平指導部にとって必ずしも目新しいものではない。2017年に米国大統領となったドナルド・トランプは、中国に対してあからさまな関税戦争を仕掛けただけでなく、安全保障を理由にしてファーウェイを排除するなど、ハイテク分野でデカップリング政策を進めた。これを受け、2020年5月頃から中国共産党の公式文書の中で「双循環」という言葉が使われ始めるようになる。国内循環(内需拡大)と国際循環(対外開放の加速)を同時に進めるという意味だ。文字面からはわかりにくいが、「双循環」という言葉の中には〈自国経済の技術力や生産性を高め、ハイテク分野等安全保障に直結する分野で部品等の内製化やサプライチェーンの安定化を図る〉という狙いが込められていた。ただし、これまでのところ「双循環」戦略の具体的な中身はあまりはっきりせず、スローガンの域を出ないという見方があったことも事実である。今般のウクライナ戦争におけるロシアの苦境を目の当たりにして、中国指導部は「不退転の覚悟で『双循環』戦略を進める必要がある」と決意を新たにしたに違いない。
《前途多難》
とは言え、双循環の先行きは前途多難であろう。中国はこれまでグローバリゼーションの恩恵を最も受けてきた国の一つだ。経済自立化の具体的な道筋を描くことは簡単ではない。最近、中国経済については「習近平体制の下で国家統制色が強まることにより、今後、自由な技術革新が阻害される」という指摘が目立ち始めている。中国の技術力も分野によって〈まだら模様〉だし、一人勝ちと言えるような状況ではない。例えば、先端半導体の製造技術は台湾がリードし、スマホ等のOS特許も米国陣営が押さえている。中国製のmRNAコロナワクチンもまだ開発されていない。米陣営の技術力の蓄積――キラー特許を含む――には端倪すべからざるものが多い。
デジタル人民元や仮想通貨を含め、中国が米ドル覇権を崩すための取り組みも決して容易なことではない。米ドルから人民元へ決済通貨を切り替えれば、「いざと言う時、米国政府の代わりに中国政府から圧力を受ける」ことになる。ロシアや一部の国を別にすれば、それを良しとする国や企業はそれほど多くあるまい。
《潜在的可能性》
中国のハイテク経済が米陣営から〈独立〉するためには、ゲーム・チャンジャー的な技術革新を幾つも実現する必要がある。そのハードルは決して低くない。だが近年、特許件数では中国企業が米国企業を抜いて第1位になっていることを考えれば、荒唐無稽な話とも言い切れない。中国には、14億人の巨大な自国市場を擁するという、他国にはない強みもある。政治・社会の分断化が止まらない米国と比べ、中期的に見た時の政治体制の安定度でも中国の方が有利かもしれない。例えば、スマートシティなどは権威主義体制の下で号令一下進められる中国での方が日米などよりもずっと早く普及し、試行錯誤で実験を重ねることができる。技術的にも価格的にも中国が世界最先端を行く可能性は十分にあるだろう。
日本政府は今、「中国憎し」と「米国のバスに乗り遅れるな」で中国経済の封じ込めにシャカリキになっているように見える。だが、中国企業の技術力が(例えば先端半導体など)複数の分野でブレークスルーを実現し、日米を凌駕するようなリスク・シナリオを想定し、その対策を練っているとはとても思えない。万が一にもハイテク分野で世界経済が米中二陣営にブロック化して市場が縮小したり、中国製の「安くて品質の良い」製品を使えないことで日本企業が国際競争上不利になったりすれば、まさに悪夢である。我々は中国の経済自立化の動きに重大な関心を寄せ、注視していく必要がある。
《エネルギー面の自立》
一方で、エネルギー供給面での自立化は急速に進むかもしれない。今日、中国の液化天然ガスの輸入はオーストラリアに4割、米国に1割強を依存しているが、今後はロシアからの輸入が急拡大する見込みだ。[ix] より根本的には、中国は2060年までには総電力量の9割を風力、太陽光、水力、原子力で賄うことを計画している。[x] これは元々、地球温暖化対策の観点から策定されたものだった。しかし、化石エネルギーからの脱却はエネルギー供給の自立化でもある。今後、中国は安全保障面での脆弱性回避という側面からも脱化石エネルギーを加速し、結果的には気候変動化対策の先進国となるかもしれない。
3. 外交的孤立回避に動くか?
中国が取り組む〈軍事力のさらなる改善〉や〈経済的自立の達成〉には、首尾よく運んだ場合でも相当な時間がかかる。それまでの間に台湾独立に伴う有事が起きた場合、軍事的にはもちろん、経済・金融制裁の面からも、中国は難儀することが避けられない。プーチンのロシアが陥ったような外交的孤立は何としても避けたいところであろう。
《欧州・日本・インドとの関係改善?》
中国が今後、一帯一路を介して東南アジアの一部、中央アジア、アフリカ諸国等を自らの勢力圏に組み込む動きを強めることは確実であろう。また、中露関係も一定の節度を保ちながら、特に経済面で緊密化が進むかもしれない。[xi] ただし、そうなったとしてもロシア経済が世界全体に占める比率は1.5%にも満たない。(そんなことは起きないが)アフリカを全部取ったところで、世界のGDPの約3%程度である。台湾有事における経済・金融制裁への対応を視野に入れた時、中国の孤立解消には全然足りない。
中国指導部が冷静かつ合理的であれば、少なくとも当面の間、所謂〈西側〉の中に味方を作るか、味方ではないまでも中立的な勢力を確保しておきたいと考えるはずである。実際に中国国内からは、「ウクライナ戦争を受け、中国は対欧州(EU)関係の安定化やインド・日本との関係改善を図るべきである」という主張が聞こえてくる。[xii] 対中脅威論と日米同盟しか眼中にないように見える日本はいざ知らず、欧州(独仏)やインドはウクライナ戦争を経ても米国ベッタリの路線はとらない可能性が高い。中国の狙いが成就する余地はある。
中国の外交力の源泉と言えば、何と言っても巨大な経済力だ。しかし、既に述べたように米欧日では外交政策を決する際に、民主主義や人権といった価値観を経済的利害関係よりも前面に出す傾向が強まってきている。これは中国外交にとって都合のよくない話だ。一方で今日、日本は言うに及ばず、米国でも欧州でも反中・嫌中感情が非常に強い。「中国に厳しく当たった方が有権者の〈受け〉がよい」という現象は、西側民主主義国家のほぼすべてで共通して見られる。中国が西側諸国の間で自国寄りの国を作ろうと思えば、米欧日の世論対策が不可欠になる。
《戦狼外交の見直しはあるか?》
中国が本気で西側世論の軟化を誘おうと思えば、西側諸国で行われる対中批判にSNS等を通じて激越な反応を示し、西側世論を挑発する「戦狼外交」の見直しは避けて通れないはずだ。だが、これが何とも見通しがきかない。過去数年を振り返ってみても、中国のベテラン外交官などから「戦狼外交は中国の国益を損なっている」という批判は少なからず出ていた。にもかかわらず、戦狼外交が下火になることはなかった。
戦狼外交が生まれた背景には、中国の国力の伸長に伴う自信とプライドの増大や、にもかかわらず欧米諸国が中国を対等な大国として受け入れようとしないことへの苛立ちがあると言われる。昨年7月に行われた中国共産党創立100周年祝賀大会で習近平は「中華民族の偉大な復興」に何度も言及し、「四つの自信」(=中国の特色ある社会主義の道の自信、理論の自信、制度の自信、文化の自信〉を固めると宣言した。習は「教師面をした居丈高なお説教は断じて受け入れない」「中国人民はいかなる外部勢力がわれわれをいじめ、抑圧し、隷属させることも決して許さない。そのような妄想を抱く者はだれであれ、必ずや14億余の中国人民が血と肉で築いた鋼の長城に頭をぶつけ、血を流すだろう」とも述べている。戦狼外交はこうした共産党の大方針とベクトルが合致している。戦狼外交官は出世が早いと言われるのも、戦狼外交が共産党指導部の中枢から支持されていることを示唆している。[xiii] 戦狼外交が中国国内で評判のよいことは言うまでもない。
ウクライナ戦争におけるプーチンの苦境を見た習近平が台湾有事や米中対立の行く末に大きな危機感を抱いていることは間違いない。だが問題は、〈その危機感が習自身の鼓舞してきたナショナリズムを土台とする好戦的な外交方針を修正するほどに大きいか否か〉である。はたして中国は戦狼外交を見直してまで、欧州や日本との関係改善に動くのか? 現時点では何とも言えない。
軍拡加速時代の幕開け
本稿を読んで勘違いしてもらいたくないのだが、今後、軍拡路線をひた走るのは決して中国だけではない。米国も、日本も、〈軍拡まっしぐら〉となりそうだ。
3月28日、予算教書を発表したバイデン大統領は2023会計年度の国防費として前年度比4%増の8,130億ドル(約100兆円)を要求した。元々、バイデン政権下における国防予算は民主党進歩派の声を反映し、横這いか微減になると言われていた。しかし、ウクライナ戦争を受けてバイデンも軍拡に舵を切った形である。
日本も近年は当初予算と補正予算の合算で防衛費の対GDP比1%越え(日本基準)が常態化している。自民党は昨年の衆院選で防衛費の対GDP比をNATO基準で(2021年度の約1.24%から)2%以上に増やすと公約した。ウクライナ戦争が勃発するや、安倍晋三元総理などはますますヒートアップし、来年度の防衛予算は当初予算で6兆円越えにすべきだと主張している。実現すれば、単純計算で年率11%超の伸び率となる。世界に目を転じれば、例えばドイツは国防予算の対GDP比を現在の1.5%程度から2%に引き上げる方針を決めた。ウクライナ戦争は、東アジアのみならず、世界中で軍拡が加速する時代の幕を開けたと言ってよい。
問題は、軍拡によって我々は安全になるのか、ということだ。[1][xiv] 単細胞の政治屋たちは「軍事力の増強によって中国を抑止できる」とほざいている。しかし、台湾が独立の動きを強めれば、中国はコストを度外視して武力行使する。それに伴って米国が軍事介入すれば、勝敗の如何に関わらず在日米軍基地を擁する日本は人的・物理的・経済的・財政的に耐えがたい損害を被る。台湾有事は〈起こしたら負け〉だ。にもかかわらず、抑止力を唱える連中の多くは、台湾独立を煽っては悦に入っている。まったくもって救いようがない。
おわりに
最後に、今年3月1日付でThe National Interest という雑誌に載ったポール・ヒアー(Paul Heer)の論考を紹介し、本稿を終えたい。[xv] ヒアーは2007年から2015年まで米国家情報会議等で東アジア担当情報官を務めた人物で、現在はCenter for the National Interest(旧ニクソン・センター)の特別研究員である。
ヒアーは、ロシアがウクライナに侵攻した最大の理由の一つは〈冷戦後、NATOの東方拡大に関するロシアの不安を米欧が無視し続けたことにある〉と主張する。対ソ封じ込め政策の生みの親であったジョージ・ケナンは1997年に「NATO拡大はロシアでナショナリズム、反西側感情、軍事志向を強め、冷戦の雰囲気を復活させ、ロシアの外交政策を米国が望むのと逆の方向に向かわせるだろう」と予言していた。その後、2008年にはNATO首脳会議でウクライナとジョージアの将来的なNATO加盟が認められた。当時のロシア大使だったウィリアム・バーンズ(現CIA長官)は「そんなことをすれば、ロシアはクリミアやウクライナ東部に干渉し、ジョージアとの間で戦争が起きる」と公電を打つ。しかし、退任間際でレガシーを作りたかったブッシュ大統領は警告を無視した。[xvi] その後もNATO拡大の動きは止まらず、ロシアはさらに不安を募らせた。そして、我慢の限界にきたプーチンはウクライナに侵攻した。今日、日本で好んで語られるストーリー(=「悪の独裁者プーチンが民主主義のウクライナを侵略した)とは異なるが、ヒアーの説明は史実に照らして正しい。[xvii]
次にヒアーは目を米中台に転じる。1972年にニクソンが訪中した時、米中は上海コミュニケを発表して「一つの中国」の原則を確認した。だが近年、トランプ政権もバイデン政権も「一つの中国」を維持していると言いながら、台湾の地位を徐々に格上げしている。これに対し、中国側は米台の動きが昂じて台湾の独立に繋がらないかと不安を募らせている。中国の我慢が限界に達すれば、ここでも武力行使が現実になりかねない。ヒアーはロシアと中国の不安(insecurity)に注目し、米国がウクライナ戦争から汲み取るべき教訓は〈軍事大国の不安を(必要以上に)煽らないこと〉だと主張している。
中国はウクライナ戦争におけるロシアの苦境を見て、米国の実力と西側陣営が団結した時の経済制裁の威力を見直している可能性が高い。本来なら、米国や日本は中国に対してある程度余裕を持ち、冷静な対応に出てもよいはずである。日米は中国に対して抑止力強化一辺倒で臨むのではなく、中国を安心させる(reassure)シグナルを適宜投げかけ、その反応を見極めるべきだ。中国の不安を取り除くうえで最大のポイントは「一つの中国」の原則を守ることを〈行動で示す〉ことにほかならない。我々は今、ウクライナ戦争という人類史上に残る悲劇を目撃している。台湾をめぐって同じような悲劇を繰り返せば、後世の人は我々を愚か者と呼ぶことだろう。
[i] https://esc.nccu.edu.tw/upload/44/doc/6963/Tondu202112.jpg なお、「可及的速やかな中台統一」と望む者は1.4%、「現状を維持しつつ、統一に向かう」は6.0%であった。
[ii] 中立を望む人の割合は、2012年の42%から2016年には25%へ低下した。Support for joining NATO at a historical high in Ukraine | Infographic | Euromaidan Press
[iii] • Ukraine: opinion on NATO accession 2021 | Statista
[iv] Global nuclear arsenals grow as states continue to modernize–New SIPRI Yearbook out now | SIPRI
[v] 2021 CMPR FINAL (defense.gov) なお、当該報告書には米軍が国防予算を増額するのに都合のよい内容が盛り込まれる傾向がある。その点は割り引いて読むのが賢明であろう。
[vi] 数字はストックホルム国際平和研究所(SIPRI)の推計に基づくもの。SIPRI-Milex-data-1949-2020_0.xlsx (live.com) なお、軍事費はあくまでも軍事力を評価するための複数の指標の一つと位置付けられるべきである。人件費等を含む軍事費の多寡によってのみ、各国の軍事的な〈強さ〉を断定する姿勢は持つべきでない。
[vii] SIPRIによる。SACO経費を含み、旧軍人恩給を除く。
[viii] SIPRI、前掲による。
[ix] 中国、ロシアのガス輸入拡大構想 パイプライン整備進む: 日本経済新聞 (nikkei.com)
[x] China is Redrawing the World’s Energy Map – Bloomberg
[xi] 現時点では、今後の中露関係が一方的に緊密化するという見方に私は懐疑的である。中国は対露関係を一方的に緊密化し、米欧から敵視されることを嫌うはずだ。また、中国とロシアは双方が相手に対して歴史的・地政学的な警戒感を抱いていると言われる。
[xii] What Lessons Does Putin’s War in Ukraine Teach China? (foreignpolicy.com) 中国人の文献としては、huang jing: opportunities, challenges and choices brought to china by the russo-ukrainian war (cfisnet.com) ←Google翻訳で英訳すれば読みやすい。(日本語訳は劣る。)
[xiii] Understanding Chinese “Wolf Warrior Diplomacy” – The National Bureau of Asian Research (NBR)
[xiv] バイデンの予算教書には富裕層と大企業向けの増税案が含まれている。しかし、自民党による防衛予算の大増額提案には財源のザの字も出てこない。どうせ赤字国債で将来世代に付け回しするつもりなのであろう。コロナでバラマキまくったうえに防衛費の大盤振る舞いに及び、一切合切を将来の税収増で賄うと言うのは詐欺に等しい。言葉遊びの「新しい資本主義」で経済成長が実現するわけもなく、日本経済は今後数十年、低成長が続くことが世界のコンセンサスとなっている。昨今の円安もその見方の反映である。防衛費は構造上、一度増やすとなかなか減らせない。日本の場合、防衛費を持続的に増やし続けることができるのか、という問題も実は極めて深刻だ。
[xv] The Real Lesson for Taiwan From Ukraine | The National Interest
[xvi] William J. Burns on Putin and Russia – The Atlantic
[xvii] 「NATO拡大に対するプーチン(ロシア)の不安を米欧が無視し続けた」というストーリーを突き詰めれば、「プーチンのウクライナ侵攻は米欧の政策上の誤りの結果である」という主張につながる。それでは日米両政府や外交サークルにとって都合が悪い。